今回の記事はこんな人におすすめ
- 計装に携わって間もない人
- 計装について理解を深めたい人
- 今よりも成長したい人
あなたは計装図という言葉を知っていますか?
 ぴよ
ぴよ・知っているけど、何が書いてあるかイマイチわからない。
・もう少しで理解できそうなんだけどな~。
・どういう時に見ると良いのかな?
このように様々な悩みや理解はしてても仕事とうまく結びつかないなんて人もいますよね?
計装工事歴16年の私が現場ではどのような時にこの計装図を使っているのかを分かりやすく、お伝えしていこうと思います。
この記事を読み終える頃には『計装図なんて楽勝だ!』とまではいかなくても、あなたにとって今よりもう少し成長できる。
『ここから先は自分でも深く学んでいけそう!』というところまでにはなっていると思います。
計装屋にとって重要な知識の三大栄養素『計装図の理解』『管理点数表の理解』『盤図(シーケンス)の理解』のうちの1つです。
一緒に勉強して学んでいきましょう。
では、本題に入ります。
計装図とは
計装図とは施主(お客様)が『どういう建物にしようか?』をわかりやすくした説明書です。
計装屋にとっての説明書でもありますので、それを元に配線などの工事をしていくという流れになります。
計装工事に必要な情報は大きく分けて5個存在します。
- 制御内容
- 自動制御機器の種類
- 自動制御機器の設置場所
- 配線の線種や部材関係
- 配線の目的地
正確に言うと線種や目的地は他の資料と合わせることでより、確信を得てから材料などは頼むのでざっくりとわかるって感じになりますね。



たくさんの現場をやっていくうちに『あ~今回はこんな感じの工事内容ね~』っていう感じですぐに頭に入ります。
計装図の見方解説
では、実際に計装図を見ながら理解を深めていきましょう。
建物の中でも割と出番の多い計装図を例に出して勉強していきましょう。
1.モジュールチラーの計装図


上記の画像はモジュールチラーと呼ばれる熱源機械廻りの計装図になります。
青色で書かれている線は設備屋さんが行う配管を記しています。
矢印方向に水が流れているのが理解できますかね?
青丸で囲っているCHSとCHRは水の流れを表しています。
CHS:Cold or hot water Send (冷水か温水を送る)
CHR:Cold or hot water Return(冷水か温水が還る)



※CHSのSがsupply(供給する)という方もいますが、まぁどちらでも意味は同じで往き側の水の流れを意味します。
次に下記の画像を見てください。


赤い丸をしている物が計装工事に必要な情報となります。
記号で書いているのは自動制御機器になります。(センサーや二方弁などのバルブ類)
TEW:配管挿入型の温度センサー
FMM:流量計
MVM:バイパス弁
PE:圧力センサー(SとRが付いているのは配管と同じ往きと還りを表しています)
この画像を見ると配管の往き側(CHS)側に温度センサーと配管の還り側(CHR)に温度センサーと流量計が設置されることがわかります。
また、ヘッダーと呼ばれるところを見ると、往きヘッダーにPESが一つと還りヘッダーにPERが1つ付いていますね。
最後にヘッダー通しを繋いているバイパスにMVMが一つついています。
これらを元に制御を見ていくと・・・
- 往きと還りの温度を見ていることから温度差を見て温めたり冷やしたりという温度制御を行っていることがわかります。
- 還り流量を見ているということは温度差と流量で熱量を見ていることがわかります。
- 往きの圧力と還りの圧力を見ているのはバイパス弁を制御する為だとわかります。



そんなのわかるわけないだろ!
初心者でもわかるように噛み砕いてくれ!
という方の為にもう少し詳しく話していきます。
往き・還りの温度差はなにを表しているのか? 詳しいバージョン
まずはチラーと空調機の関係性について必要があります。
- チラーで冷水を作る
- 冷水が配管を通じて空調機のコイルに入る
- その冷水入りの冷たいコイルに空調機で風を当てる
- 涼しい風が出る
- 涼しい風はダクトを通じて部屋に入る
- 部屋は冷えると同時に温かい風を還りのダクトに押し込む
- 温かい風をまた冷えたコイルに当てる
- 涼しい風が出る(2週目)
- 涼しい風はダクトを通じて部屋に入る(2週目)
- 部屋は冷えると同時に温かい風を還りのダクトに押し込む(2週目)
これの繰り返しになります。
下記の画像で見てもらうとイメージしやすいかもです。


話を戻しますが、還りの配管の温度は部屋の暖かい風が当たる為にぬるい温度でチラーに戻っていきますよね?
ぬるくなるということ=部屋が暑いということになります。
逆に部屋が冷たい場合は空調機に冷たい風が入ってくるので、冷たい風をコイルに当ててもコイルはぬるくならず、冷えたままチラーに戻ってくることがわかりますよね?
往きの配管温度と還りの配管温度で部屋の温度制御をするというのはこういう意味になります。
温水の場合は冷水と真逆なことが行われているだけです。
往きと還りの圧力でバイパス弁を制御する? 詳しいバージョン
まずは下記の画像を見てください。


冷温水配管が仮に何かしらの影響で配管が詰まった場合でも、チラーは先ほどの空調機のコイルに水を送ろうとポンプを回しますが、詰まっているのでどんどん水が詰まっていきます。
そうすると配管内はものすごい圧力になることがわかりますか?
それでも無理やりにポンプは水を押し込もうとするので、ポンプがそのうちに焼けてしまうんですね。
往きヘッダーの圧力がどんどん上がっていくのに対して、還りは詰まっているせいで水が来ない状態。
つまり還りのヘッダーには圧がない状態になりますね。
この圧力差が出た際にバイパス弁を開いて水を逃がしてあげる制御をバイパス制御と言います。
画像でいうところの赤い線の部分に水を流してあげることで水をぐるぐる循環させることができるので、ポンプが壊れる心配がなくなるというものです。



②の温度差と流量で熱量を出すというのは計測であって制御ではないので、特に説明は不要なので省略します。
熱量計算は物理?か理科の授業でやったはずなので、調べて見てください。
現場では機械が演算しますので熱量計算を使う場面はありません。
話が長くなりましたが、先ほど述べた下記の件が計装図を見ることによってわかる理由は納得できましたか?
- 往きと還りの温度を見ていることから温度差を見て温めたり冷やしたりという温度制御を行っていることがわかります。
- 還り流量を見ているということは温度差と流量で熱量を出すことができますよね?を見ていることがわかります。
- 往きの圧力と還りの圧力を見ているのはバイパス弁を制御するためだとわかります。
まとめ
【初心者でもわかる】計装図とは何か?読み方を一から学ぼう!というテーマで今回記事を書かせていただきました。
ポイントはこれ
計装工事に必要な情報は大きく分けて5個存在します。
- 制御内容
- 自動制御機器の種類
- 自動制御機器の設置場所
- 配線の線種や部材関係
- 配線の目的地
※ただし、配線の種類と目的地は知識の三大栄養素を合わせて見ないといけないのでざっくりとしたイメージ
計装図の見方については今回はモジュールチラーでお話しさせてもらいました。
もっと細かく知りたい人や、他の機器の制御も気になる方は設備機器の方で各機器詳しく解説しています。
今回の勉強は計装屋にとって重要な知識の三大栄養素『計装図の理解』『管理点数表の理解』『盤図(シーケンス)の理解』のうちの1つです。
初心者の方も経験者でも『今回の内容知らなかったよ』って方はこれからも一緒に勉強していきましょう。
最後まで記事を読んでくれてありがとうございました。
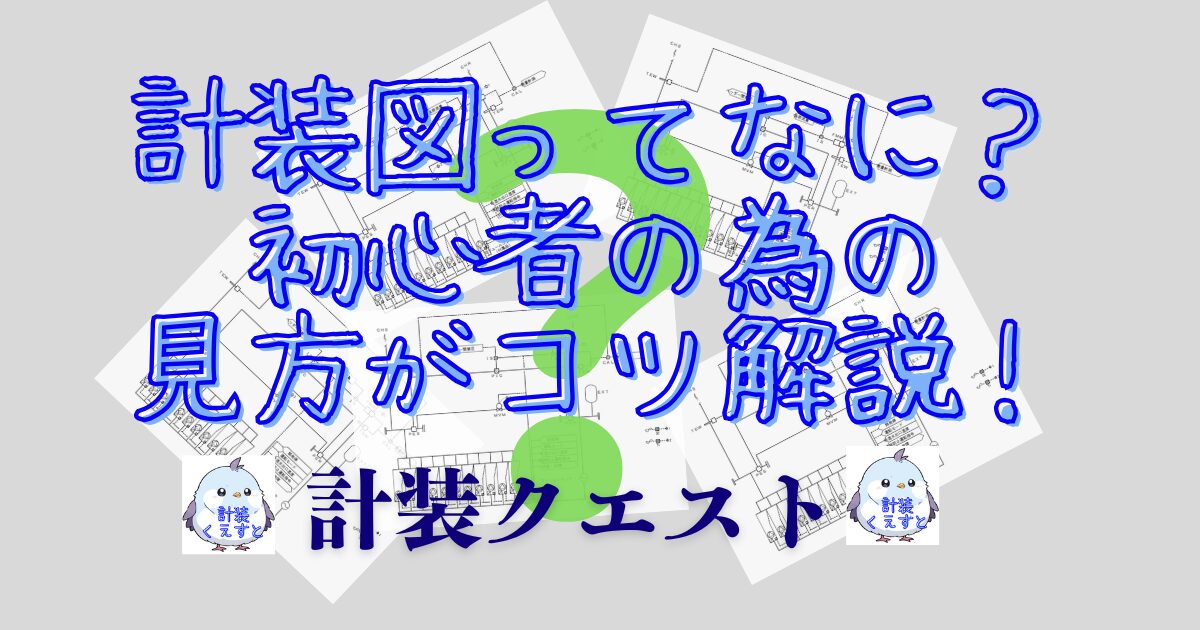

コメント